SS
桜を彫りたい紅丸の話7
――危なかった。
紺炉が出て行った後、部屋で一人になった桜備は机に両肘をついて項垂れ、安堵の息を吐いた。
恐らく、あの世話人は自らの主人の奇行にも、その原因にも気づいている。
人並の恋愛経験を有し、惚れる方と惚れられる方どちらの立場も経験がある桜備にとってみても、紅丸の態度はあからさまだった。立場や年齢や性別や、否定するための要素をすべて無意味と取り去ってしまえば、それはあまりにも明らかだ。無意味と取り去った方が話が早い、そういう規格外の相手でもある。
ただでさえ、新門紅丸という男は人の好き嫌いが分かりやすい。嫌いな人間は徹底的に嫌いだし、好きな人間はあっさりと懐に迎え入れ等しく愛する。
等しく愛されている内の一人。そうだったはずが、どこで、いつのまに変わってしまったのだろう。相手の変化のきっかけは分からないが、それに桜備が気がついた瞬間は覚えている。
浅草上空に現れた巨大な鳥を総出で退治し、そのままソイツを丸焼きにして宴会に興じた夜のことだった。時間も遅くなり、次の日早朝から予定が入っていた桜備は頃合いを見て中座しようと腰を上げた。それを引き留めようと、グイ、と緩いズボンの裾を引っ張っていたのは紅丸の手だった。
「まだいいだろ」
スクワットのような中途半端な体勢で固まった桜備の顔を見上げる。それまでは酒が入ってニコニコと笑っていたはずが真顔に戻り、瞼に隠れていた左右非対称な瞳が開いている。眉根にはシワがより、まさか怒っているのかと心配になる表情だったが、酔っているのは間違いないようで、赤く染まった頬が怒るというよりは拗ねた子供じみたかわいらさに和らげていた。
「明日、朝早いんでこれ以上はちょっと……」
紅丸は酒の席に限界ギリギリまで留まる方だし、宴会には人が多ければ多いほど良いと思っているタイプではあるが、他人に無理強いすることはない。というより、誰がいつ来ていつ帰ったのかなど把握していない。だから、この時の対応は桜備にとってかなり予想外だった。
「いやだ」
振り払いたくても振り払えないくらい本気の力で掴まれた裾を、一体どうやって引き剥がしたのかはよく覚えていない。今になって思う。あの時引き留めに応じて帰らないのが正しい選択だったかもしれない。手に入らなかった経験が余計に欲を燃え上がらせるのはよくあることだ。
あの一件以来、紅丸の態度や視線に欲の混じった色を感じる瞬間が増えた。若さとは恐ろしい。ギラギラと光る欲の刀を大人しく鞘に仕舞っておくなどできないのだろう。
気づいていない振りでやり過ごせればそれはそれで。そう考えてのらくらしていたところで、今日の紺炉の様子伺いは耳が痛かった。とはいえ、紅丸の変化を察せれるとすれば彼しかいない。真っ先に気づくだろう人物に気づかれただけ。まだ状況は深刻ではないのだ。なにか問題があるとすれば――
「俺、喜んじゃってんだよなぁ……大人としてどうなんだ?」
うんうんと悩みながらも、耳は扉の外のざわめきに注意を向いていた。さっき部屋を出た紺炉と、恐らく火縄が、さっきから何やら話している。内容までは聞き取れないが、言葉が途切れ遠ざかる足音が聞こえて、会話の終わりを察する。パン、と両頬を手の平で打ち付け気合いを入れる。
自らの動揺を悟られるようなことだけは避けなくては。そう気合いを入れ、予想通りのタイミングで鳴った火縄特有の固く鋭いノックの音に、どうぞ、と大きな声で返した。
畳む
――危なかった。
紺炉が出て行った後、部屋で一人になった桜備は机に両肘をついて項垂れ、安堵の息を吐いた。
恐らく、あの世話人は自らの主人の奇行にも、その原因にも気づいている。
人並の恋愛経験を有し、惚れる方と惚れられる方どちらの立場も経験がある桜備にとってみても、紅丸の態度はあからさまだった。立場や年齢や性別や、否定するための要素をすべて無意味と取り去ってしまえば、それはあまりにも明らかだ。無意味と取り去った方が話が早い、そういう規格外の相手でもある。
ただでさえ、新門紅丸という男は人の好き嫌いが分かりやすい。嫌いな人間は徹底的に嫌いだし、好きな人間はあっさりと懐に迎え入れ等しく愛する。
等しく愛されている内の一人。そうだったはずが、どこで、いつのまに変わってしまったのだろう。相手の変化のきっかけは分からないが、それに桜備が気がついた瞬間は覚えている。
浅草上空に現れた巨大な鳥を総出で退治し、そのままソイツを丸焼きにして宴会に興じた夜のことだった。時間も遅くなり、次の日早朝から予定が入っていた桜備は頃合いを見て中座しようと腰を上げた。それを引き留めようと、グイ、と緩いズボンの裾を引っ張っていたのは紅丸の手だった。
「まだいいだろ」
スクワットのような中途半端な体勢で固まった桜備の顔を見上げる。それまでは酒が入ってニコニコと笑っていたはずが真顔に戻り、瞼に隠れていた左右非対称な瞳が開いている。眉根にはシワがより、まさか怒っているのかと心配になる表情だったが、酔っているのは間違いないようで、赤く染まった頬が怒るというよりは拗ねた子供じみたかわいらさに和らげていた。
「明日、朝早いんでこれ以上はちょっと……」
紅丸は酒の席に限界ギリギリまで留まる方だし、宴会には人が多ければ多いほど良いと思っているタイプではあるが、他人に無理強いすることはない。というより、誰がいつ来ていつ帰ったのかなど把握していない。だから、この時の対応は桜備にとってかなり予想外だった。
「いやだ」
振り払いたくても振り払えないくらい本気の力で掴まれた裾を、一体どうやって引き剥がしたのかはよく覚えていない。今になって思う。あの時引き留めに応じて帰らないのが正しい選択だったかもしれない。手に入らなかった経験が余計に欲を燃え上がらせるのはよくあることだ。
あの一件以来、紅丸の態度や視線に欲の混じった色を感じる瞬間が増えた。若さとは恐ろしい。ギラギラと光る欲の刀を大人しく鞘に仕舞っておくなどできないのだろう。
気づいていない振りでやり過ごせればそれはそれで。そう考えてのらくらしていたところで、今日の紺炉の様子伺いは耳が痛かった。とはいえ、紅丸の変化を察せれるとすれば彼しかいない。真っ先に気づくだろう人物に気づかれただけ。まだ状況は深刻ではないのだ。なにか問題があるとすれば――
「俺、喜んじゃってんだよなぁ……大人としてどうなんだ?」
うんうんと悩みながらも、耳は扉の外のざわめきに注意を向いていた。さっき部屋を出た紺炉と、恐らく火縄が、さっきから何やら話している。内容までは聞き取れないが、言葉が途切れ遠ざかる足音が聞こえて、会話の終わりを察する。パン、と両頬を手の平で打ち付け気合いを入れる。
自らの動揺を悟られるようなことだけは避けなくては。そう気合いを入れ、予想通りのタイミングで鳴った火縄特有の固く鋭いノックの音に、どうぞ、と大きな声で返した。
畳む
SS
桜を彫りたい紅丸の話6
「なにが思い過ごしなんですか」
独り言のつもりで呟いた紺炉は、ふいに話しかけられて、ギョッと驚き眉を吊り上げた。
「驚いた。いたのかい」
「通りがかったんです。総隊長に用があるので」
いつの間にか横にいた火縄は、いつも通りの淡々とした口調で答えながら、紺炉の背中のすぐ後ろにある扉を人差し指で指し示した。
「今日はどうなさったんですか?」
「ああ、ちょっとばかしお礼と、あと花見の相談を」
「まだ正月も過ぎたばっかりだっていうのに、浅草の人は気が早いですね」
皮肉というより、本気で感心している様子で火縄が驚く。眼光鋭く言葉に棘はあるものの、真面目な男だ。
「そういや子供が産まれるんだって? めでてェこった」
「無事に産まれるまではめでたくもなんともありません。死がフワッフワに軽くなったこの世界で、生の重みは余計増していると考えていますから」
表情を変えずに言い切り、クイ、と眼鏡のフレームを指で押し上げる。少し俯いた顔の眼光が幾分落ち着き、わずかに不安までもが滲んでいるのが紺炉からすると意外だった。
「総隊長とはお話を?」
「まあ、ほんの数分ってとこだが」
「……紺炉指揮官補佐から見て、総隊長に何か変わった様子はありませんか?」
火縄のその質問に引っかかりを覚えた紺炉は、思わず首を捻った。奇しくもついさっき自分が桜備に尋ねたのとほとんど同じ質問だったからだ。
「何か、ってェと……」
「特に無ければ構いません。忘れてください」
言い淀む紺炉を待たず早々に切り捨てる。まるで自分の質問が失言だったとすぐに気づいたかのような火縄の様子に、ますます疑念が募る。
「……お互い、頭がジッとしてられる性質じゃないから苦労するな。世界はすっかり変わったってのに、あの人らはまるで変わりやしねェで、こっちが思いも寄らないことばっかり考えつきやがる」
「……全くです」
「……お前さん的にはいいのかい?」
紺炉が探り探りに投げた質問に対して、火縄は頬も眉もピクリとも動かさないまま、素早いまばたきを数度繰り返した。まるで、人間の及ばない素早さで結果を求めているこんぴゅうたあのようだ。妙な状況に陥って、答えを待つ紺炉の額には冷や汗が伝っていた。
数秒後、火縄は計算の終わりを示すかのように眼鏡のフレームを押し上げてから口を開いた。
「あの二人は今やほとんど神に匹敵する力があります。つまり、喧嘩にでもなれば世界の半分くらいは滅んでも不思議じゃない。仲が良いのに越したことはないでしょう」
予想外の答えに呆気に取られた紺炉は、一瞬息を呑んでからすぐに我に返り、ワハハハと声に出して豪快に笑った。
「ちげェねェな! 犬も喰わねえような喧嘩だけは勘弁してほしいところだ」
それから「あんたも花見絶対来いよ」と言い置き、笑顔を浮かべたまま廊下を玄関に向かって歩きだした。
畳む
「なにが思い過ごしなんですか」
独り言のつもりで呟いた紺炉は、ふいに話しかけられて、ギョッと驚き眉を吊り上げた。
「驚いた。いたのかい」
「通りがかったんです。総隊長に用があるので」
いつの間にか横にいた火縄は、いつも通りの淡々とした口調で答えながら、紺炉の背中のすぐ後ろにある扉を人差し指で指し示した。
「今日はどうなさったんですか?」
「ああ、ちょっとばかしお礼と、あと花見の相談を」
「まだ正月も過ぎたばっかりだっていうのに、浅草の人は気が早いですね」
皮肉というより、本気で感心している様子で火縄が驚く。眼光鋭く言葉に棘はあるものの、真面目な男だ。
「そういや子供が産まれるんだって? めでてェこった」
「無事に産まれるまではめでたくもなんともありません。死がフワッフワに軽くなったこの世界で、生の重みは余計増していると考えていますから」
表情を変えずに言い切り、クイ、と眼鏡のフレームを指で押し上げる。少し俯いた顔の眼光が幾分落ち着き、わずかに不安までもが滲んでいるのが紺炉からすると意外だった。
「総隊長とはお話を?」
「まあ、ほんの数分ってとこだが」
「……紺炉指揮官補佐から見て、総隊長に何か変わった様子はありませんか?」
火縄のその質問に引っかかりを覚えた紺炉は、思わず首を捻った。奇しくもついさっき自分が桜備に尋ねたのとほとんど同じ質問だったからだ。
「何か、ってェと……」
「特に無ければ構いません。忘れてください」
言い淀む紺炉を待たず早々に切り捨てる。まるで自分の質問が失言だったとすぐに気づいたかのような火縄の様子に、ますます疑念が募る。
「……お互い、頭がジッとしてられる性質じゃないから苦労するな。世界はすっかり変わったってのに、あの人らはまるで変わりやしねェで、こっちが思いも寄らないことばっかり考えつきやがる」
「……全くです」
「……お前さん的にはいいのかい?」
紺炉が探り探りに投げた質問に対して、火縄は頬も眉もピクリとも動かさないまま、素早いまばたきを数度繰り返した。まるで、人間の及ばない素早さで結果を求めているこんぴゅうたあのようだ。妙な状況に陥って、答えを待つ紺炉の額には冷や汗が伝っていた。
数秒後、火縄は計算の終わりを示すかのように眼鏡のフレームを押し上げてから口を開いた。
「あの二人は今やほとんど神に匹敵する力があります。つまり、喧嘩にでもなれば世界の半分くらいは滅んでも不思議じゃない。仲が良いのに越したことはないでしょう」
予想外の答えに呆気に取られた紺炉は、一瞬息を呑んでからすぐに我に返り、ワハハハと声に出して豪快に笑った。
「ちげェねェな! 犬も喰わねえような喧嘩だけは勘弁してほしいところだ」
それから「あんたも花見絶対来いよ」と言い置き、笑顔を浮かべたまま廊下を玄関に向かって歩きだした。
畳む
SS
桜を彫りたい紅丸の話5
その日紺炉は、町の破壊を手伝ってもらった礼とは別に、ひとつの提案を携えて元第8特殊消防隊詰所・現世界英雄隊本部を訪れた。
「部隊合同での花見か、いいですね。折角だから送別会も兼ねて、集まれそうな人みんなに声をかけましょう」
「送別会ということは、誰か離職を?」
「ああ、退職ではないんですがマキ中隊長が来月から産休に入るんですよ。無事に産まれたら火縄も育休を取るし、しばらくの間は寂しくなりそうです」
目を細め朗らかに笑う顔は、まるで自分自身が父親になるかのように嬉しそうだった。(元)第8は隊というより家族みたいなものなのだと、そう言っていたのは修行に訪れたシンラだっただろうか。
「先日は若の酔狂にも付き合ってもらっちまって……随分派手に暴れてたけど、体は平気か?」
「全然! 賑やかなのは好きだし、良いトレーニングにもなりました。宴会までは残れなくて残念だったんで、今度の花見で雪辱を果たすつもりです。--案件としては、こんなもんですかね?」
「じゃあー、ついでにウチのしょうもない相談でも聞いてもらおうか。実は若が……」
「また何かしたんですか?」
「墨、じゃなくて……たとぅーを入れるって言い出して」
「うわっ、あの時のシンラを思い出す…! 男の子って、やっぱ一度はそういう時が来るんですかね」
「男の"子"といえる年でもないってのに」
「でも、浅草の原国式のタトゥーは粋でかっこいいじゃないですか。シンラの場合は人格もおかしくなっちゃったからイメージ悪いけど、タトゥー入れるだけだったら特段たいした問題にもならなかったかと」
説明と共にそう遠くはない記憶に思いを巡らせているのか、口の間から乾いた笑いを漏らしつつ、視線を斜め右にさ迷わせる。桜備の珍しい表情を見た紺炉も、浅草に第8が秘密基地を構えていた時に垣間見たシンラの”反抗期”をぼんやりと思い出す。
「悪いこたァないが、なにやら変な感じでね。総隊長から見て、最近若…いや、紅のことで、何か気になる節はねェかな」
「気になる?」
気になることねえ…と、縫い目のある首を見てる方が不安を覚えるほどにまで傾け考えていた桜備だったが、突然すっ、と執務机の大きな席から無言で立ちあがったと思いきや、そのまま紺炉のすぐ横にまで歩み寄ってきた。ふいの行動と詰められた距離にぎょっとした紺炉の体が、反射的に軽く強張る。
「ほら、俺たち丁度身長同じくらいでしょ。だから分かってくれるんじゃないかと思うんですけど、見上げられると照れませんか?」
「照れる?」
「こう、横並びで立ってる時なんかに、こっちを見上げてくる顔が妙に幼く見えて。酒に酔った時の笑顔もそうだけど、あんな顔されると、ちょっと調子狂いますね」
頬を指先で掻きながら照れ笑いを浮かべる桜備の細まった目。本人が言う通り紺炉の目線とほぼ同じ高さだった。その目からそろりと視線を逸らし、いつも紅丸の顔がある辺りにさ迷わせる。
あんな顔、と言われても、どんな顔か分からない。
おい紺炉、と見上げてくる紅丸を思い浮かべてみたが、それは勝気で不遜で、ある意味愛おしいくらいの生意気さに満ちている。照れるようなもんじゃない。幼い頃からよくよく知っているつもりだが、それだって今の紅丸の全てとは言い難いことを思い知らされた気がした。
「すいません。俺が言いたいのは、とどのつまり気になることはないってことです。これまでの働きにも、文句のつけようがない。この国、いや、この世界にとってお二人とも代えがたい存在です。頼りにしてます!」
距離が近いまま真剣な面持ちで言い連ねる桜備からこの男特有の妙な圧を受け、耐えきれなくなった紺炉は思わず一歩二歩と後ずさる。
そういう話ではないのだけど、と返すべきか数秒ほど逡巡し、止める。
「そりゃ、ありがたい……若にも伝えとくよ」
情人云々と、紅丸より先にこちらにカマをかけなくて良かった。いや、たとえ投げかけたとしても、元より紺炉の意図などサッパリ伝わりそうにない。
紅丸の真意の程は測りかねるが、たとえどう転んだとしても、大地に根を張る巨木のようなこの男はビクともしないだろう。
じゃあまた、とそそくさとその場を後にした紺炉は、廊下に出てからほぉ、とため息を吐いた。まるで自らがスッパリと振られたような気分になり、かえって溜飲が下がるのを感じていた。
「早とちりで、思い過ごしか。紅のこととなると心配が先立っちまってなさけねェな」
畳む
その日紺炉は、町の破壊を手伝ってもらった礼とは別に、ひとつの提案を携えて元第8特殊消防隊詰所・現世界英雄隊本部を訪れた。
「部隊合同での花見か、いいですね。折角だから送別会も兼ねて、集まれそうな人みんなに声をかけましょう」
「送別会ということは、誰か離職を?」
「ああ、退職ではないんですがマキ中隊長が来月から産休に入るんですよ。無事に産まれたら火縄も育休を取るし、しばらくの間は寂しくなりそうです」
目を細め朗らかに笑う顔は、まるで自分自身が父親になるかのように嬉しそうだった。(元)第8は隊というより家族みたいなものなのだと、そう言っていたのは修行に訪れたシンラだっただろうか。
「先日は若の酔狂にも付き合ってもらっちまって……随分派手に暴れてたけど、体は平気か?」
「全然! 賑やかなのは好きだし、良いトレーニングにもなりました。宴会までは残れなくて残念だったんで、今度の花見で雪辱を果たすつもりです。--案件としては、こんなもんですかね?」
「じゃあー、ついでにウチのしょうもない相談でも聞いてもらおうか。実は若が……」
「また何かしたんですか?」
「墨、じゃなくて……たとぅーを入れるって言い出して」
「うわっ、あの時のシンラを思い出す…! 男の子って、やっぱ一度はそういう時が来るんですかね」
「男の"子"といえる年でもないってのに」
「でも、浅草の原国式のタトゥーは粋でかっこいいじゃないですか。シンラの場合は人格もおかしくなっちゃったからイメージ悪いけど、タトゥー入れるだけだったら特段たいした問題にもならなかったかと」
説明と共にそう遠くはない記憶に思いを巡らせているのか、口の間から乾いた笑いを漏らしつつ、視線を斜め右にさ迷わせる。桜備の珍しい表情を見た紺炉も、浅草に第8が秘密基地を構えていた時に垣間見たシンラの”反抗期”をぼんやりと思い出す。
「悪いこたァないが、なにやら変な感じでね。総隊長から見て、最近若…いや、紅のことで、何か気になる節はねェかな」
「気になる?」
気になることねえ…と、縫い目のある首を見てる方が不安を覚えるほどにまで傾け考えていた桜備だったが、突然すっ、と執務机の大きな席から無言で立ちあがったと思いきや、そのまま紺炉のすぐ横にまで歩み寄ってきた。ふいの行動と詰められた距離にぎょっとした紺炉の体が、反射的に軽く強張る。
「ほら、俺たち丁度身長同じくらいでしょ。だから分かってくれるんじゃないかと思うんですけど、見上げられると照れませんか?」
「照れる?」
「こう、横並びで立ってる時なんかに、こっちを見上げてくる顔が妙に幼く見えて。酒に酔った時の笑顔もそうだけど、あんな顔されると、ちょっと調子狂いますね」
頬を指先で掻きながら照れ笑いを浮かべる桜備の細まった目。本人が言う通り紺炉の目線とほぼ同じ高さだった。その目からそろりと視線を逸らし、いつも紅丸の顔がある辺りにさ迷わせる。
あんな顔、と言われても、どんな顔か分からない。
おい紺炉、と見上げてくる紅丸を思い浮かべてみたが、それは勝気で不遜で、ある意味愛おしいくらいの生意気さに満ちている。照れるようなもんじゃない。幼い頃からよくよく知っているつもりだが、それだって今の紅丸の全てとは言い難いことを思い知らされた気がした。
「すいません。俺が言いたいのは、とどのつまり気になることはないってことです。これまでの働きにも、文句のつけようがない。この国、いや、この世界にとってお二人とも代えがたい存在です。頼りにしてます!」
距離が近いまま真剣な面持ちで言い連ねる桜備からこの男特有の妙な圧を受け、耐えきれなくなった紺炉は思わず一歩二歩と後ずさる。
そういう話ではないのだけど、と返すべきか数秒ほど逡巡し、止める。
「そりゃ、ありがたい……若にも伝えとくよ」
情人云々と、紅丸より先にこちらにカマをかけなくて良かった。いや、たとえ投げかけたとしても、元より紺炉の意図などサッパリ伝わりそうにない。
紅丸の真意の程は測りかねるが、たとえどう転んだとしても、大地に根を張る巨木のようなこの男はビクともしないだろう。
じゃあまた、とそそくさとその場を後にした紺炉は、廊下に出てからほぉ、とため息を吐いた。まるで自らがスッパリと振られたような気分になり、かえって溜飲が下がるのを感じていた。
「早とちりで、思い過ごしか。紅のこととなると心配が先立っちまってなさけねェな」
畳む
メモ
3/17 読み返しながら巻数・話数をメモってる
最後まで読んでから5~6巻辺りを読み返すと
この頃の紅丸やたら細っ白いし自信無いしでかわいい めっちゃ攻め
エピローグでは立場が上下になるけど桜備は紅丸に対して敬語のままなのかタメ口になるのか問題
結論出さずにどっちも妄想したい
42話の喧嘩で口調が荒くなるけどギリ敬語残ってるの好き…大好き
最後まで読んでから5~6巻辺りを読み返すと
この頃の紅丸やたら細っ白いし自信無いしでかわいい めっちゃ攻め
エピローグでは立場が上下になるけど桜備は紅丸に対して敬語のままなのかタメ口になるのか問題
結論出さずにどっちも妄想したい
42話の喧嘩で口調が荒くなるけどギリ敬語残ってるの好き…大好き
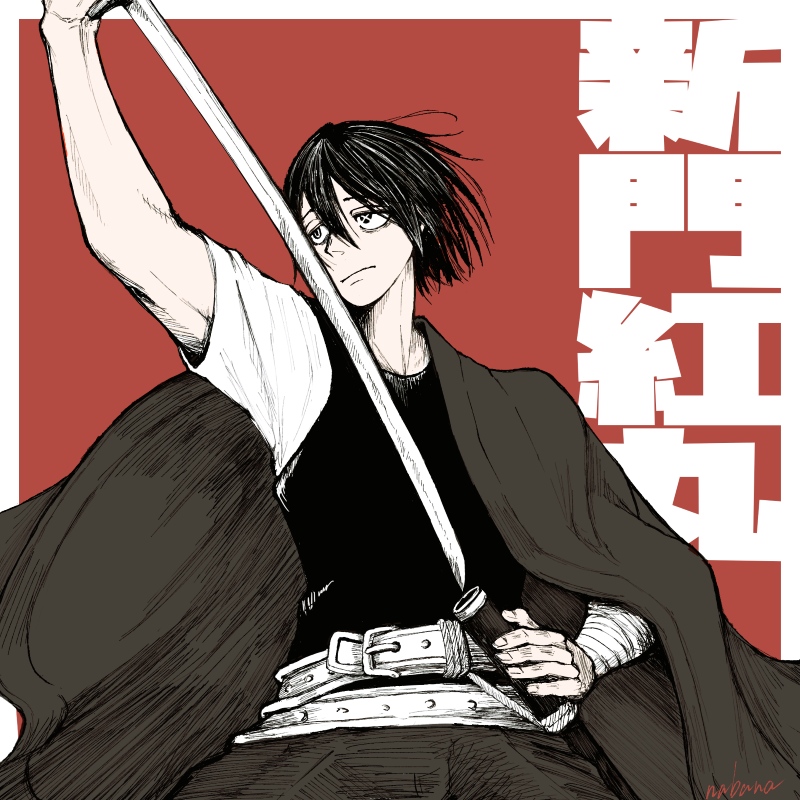
桜の花芽が膨らみ出し、朝着た上着を昼には脱ぎたくなるような日も増えて来た頃、新東京皇国に季節外れの雪が降った。
「え、高熱ですか? なにか感染症の疑いは?」
『念のため元第六のお医者さんにも診てもらったが、問題ないだろうってさ』
「なら良かった。どうせ大した会議じゃないんで、お二人とも欠席で大丈夫ですよ」
『そうさせてもらう。若は能力者の体質のせいか、昔っから熱が出やすくてね。心配するほどのもんじゃないよ』
電話口の紺炉の声色には、本人の言葉通り深刻さはまったくなかった。電話を受けていた桜備は、最後に一言二言告げてから受話器を置くと、背後に控えていた火縄を振り返った。
「新門総指揮、今朝から熱出てて会議休むって」
「へぇ。病気の方から逃げ出しそうなのに、意外ですね」
「だよな。病気を追いかけ回していじめてそうなのに」
火縄の感想に頷き同意しながらも、桜備の目はささめ雪が舞う窓の外を向いていた。心配そうな横顔を”心配そう”と認識できるのが火縄だからなのか、それとも誰の目から見ても明らかなのか、判断が微妙になる程度の表情だった。
「お見舞い、行ってきたらどうですか。どうせ大した会議じゃないですし」
「ろ……こん、ろ……みず」
布団から片手を宙へと伸ばし呻く紅丸に、はい、と茶碗が差し出される。その、はい、の声の違和感に気づき薄っすらと目を開けた紅丸は、傍らにいるのが紺炉ではないことに驚き、氷枕も掛け布団もはね除けて上体を跳ね起こした。
「なっ……!」
「うわ、びっくりした。寝てていいですよ」
「吃驚したのはこっちの方だ。てめェ何しに来た」
「何ってそりゃ、お見舞いです。あ、メロン好きですか?」
「好きじゃねえェ……けど双子は喜ぶだろ」
桜備が片手で掲げた本人の顔と同じくらいの大きさがあるメロンの球を睨み付けながら水を飲み、ノロノロと布団の中へと戻る。
「体調どうですか?」
「どうもこうもねェ。最悪だ。……そういやさっき寝てる時、つっても熱のせいで寝てるか起きてるかもよくわかんねえんだけどな。今のこれも、夢か現かわからねェ。まあとにかく、夢を見てた」
「また前みたいな実体感のある夢ですか」
「ねェよ。実体感も現実感もねェ。ガキの頃の夢なのに、お前も出てきたからな」
「へえ」
「ガキん頃の俺が、町の外れにあるがらくた置き場で能力の使い方間違ってうっかり炎上させちまう。そこを助けに来たのが皇国の消防隊様々ってわけだ。で、起きたら本人がいたもんだから、よけい吃驚したんだよ」
「なるほど」
「四方を火に囲まれて、熱い熱いって泣いてんのが情けなくって我ながらムカついた。熱のせいで見ちまった夢だな」
「ちなみにそれ、いくつぐらいの時ですか?」
「さあな。十かそこらじゃねェか? 先代も生きてたから、どんなに育ってても十三だ」
あくまでも夢の話なのにまるで実際の思い出のように話すフワフワとした紅丸の説明を受け、桜備は、ふむ、と小首を傾げながら順に指を折った。
現実感がないと言ったが、その頃の桜備はもう訓練校を卒業して一般消防官として入隊していたはずだ。あり得なくはない。が、もちろん桜備にそんな記憶はないし、そもそも紅丸が炎を怖がったことなど生まれて一度もないだろうから、そういう意味で現実感が無いのかもしれない。
「そういや聞きましたよ。タトゥー入れるって」
「紺炉か。あの馬鹿……」
「どこに入れるんですか? 腕?」
「まだ決めてねえ」
不満げなドスの効いた声で返され桜備がたじろぐと、紅丸はおもむろに自らの足で掛け布団を撥ねのけた。そのまま両手を左右に伸ばし大の字になると、天井に向かって「選べ」と宙に放るような声で言った。
「選べ。好きなとこ」
「選べ、って言われても……」
普段つけている黒い腹掛けもなく、寝乱れた浴衣の合わせ目からは首から腰までの素肌が三角形に覗いている。裸を見られるのにも見せるのにも抵抗が無い元第八の男性陣と違い、この男が必要もなく素肌を晒すのは稀だ。活動時間が夜に寄っているせいなのか生まれつきなのか、肌は不健康に青白く、そこに熱のせいでほんのりと赤みが差し、妙に人間らしい色になっている。
「布団、ちゃんとかけなさいよ」
なんとなく見てはいけないようなものに思え、本人が剥がした布団を手早く元に戻す。気恥ずかしさから、子どもを嗜めるような口調になってしまった。
「そういや知ってます? 今朝から雪降ってるの」
話題を変えようと声を張ってそう問いかけた桜備は、部屋の中央に敷かれた布団を回り込んで移動し、縁側の障子に手を掛けた。30センチほどの隙間から、薄っすらと白くなった庭と、チラチラと雪が舞う藍鼠色の空か覗く。雨と雪の境のような、氷の粒に近いみぞれ雪だ。
「すっかり春になったと思ってたってェのに。どうなってんだ」
「なごり雪ってやつですかね」
「なんだって?」
「なごり雪。こういう、季節外れに降る雪。俺はもともと歌の歌詞で知ったんですけど」
「……知らねェな。それよか、用がねェならとっとと帰れ。デカいのがいると気が散って寝れやしねェ」
寝込んでいても減らない口にはいはい、と呆れ顔で返し障子を閉めようとした桜備は、中途半端なところで手を止めた。
「……どっちなんですか」
言葉とは裏腹に、布団からはみ出した紅丸の手は桜備の服の裾をしかと掴んでいる。困惑する桜備が呟いたもっともな疑問に対しての返事はなく、そもそも言葉を発する気力すらもう無いのか、息ばかりが荒い。それでも、見下ろす桜備を見返す細まった双眸の眼光はやたらと鋭かった。
参ったな、と悩まし気に片眉を歪め目を反らし、仕方なしに、障子の隙間からふたたび外を見る。ここに来るまでの道中にくらべると雪の勢いは幾分弱まり、ハラハラと落ちる白い欠片は花びらのようにも見えた。隙間に鼻先を少し近づけると、途端に冷たい風が吹き付けてくる。
視線は移さずに、手だけを自分の腰あたりにさ迷わせた。掴まれている場所は服を引っ張られている感覚で大体分かる。だとしても、掴んでいる手を離させようとしたのか、それともただ触れたかったのか、桜備自身にも曖昧だった。そして、いざ触れた途端に感じた熱の高さにハッとし、ほんの一瞬で慌てて引っ込める。俺は一体何を――
指先の行き場に困り、火傷した時のようについ耳たぶを擦る。発火能力を失ったはずの体がこんなにも熱いのは、高熱のせいだけなのか?
「……アレ、どんな歌だったかな」
動揺を誤魔化そうという意識が働いたのか、思考は前の話題へと無理矢理に戻っていく。思い出せるのは曲名から始まる数フレーズだけだったが、試しに口ずさんでみると頭よりも口が先に動き出し、たどたどしい調子ながら恐らく合っているだろうメロディーラインを紡げた。
「まぁ、大災害より前の曲だから知らなくて当たりまえですよ。俺もたまたま見つけた古いレコードで――」
話しかけながら振り返り、いつの間にか目を閉じていた顔を見て口を止める。裾を掴んでいた手の力も完全に抜け、布団から飛び出したまま畳の上にぐたりと落ちていた。自由に動けるようになったもののすぐに立ち上がる気にはなれず、部屋の主の心地よさそうとは言い難い寝顔を眺める。
あの夜の引き留めに応じても応じなくても、多分結果は変わらなかっただろう。態度や言葉で表せるような、そんな感情はもうとうに越えている。ような気がする。
うなじを撫ぜる風は冷たいのに、顔はどんどん熱くなっているのを感じる。咲いた桜を眺めるのではなく、咲く寸前の蕾を見守っている時に近い感覚。随分と久しぶりに覚えたときめきとしか表現しようのない期待と高揚感に、自然と鼓動が速まる。
「……悪くないな」
今春が来て、そして唐突に溢れそうになった感情を持て余し、その一言を呟くので精いっぱいだった。
畳む